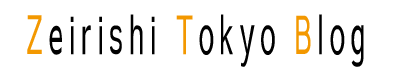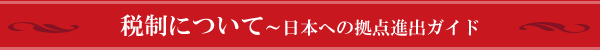
進出形態(支店か現地法人か)に対する税制の中立性
日本において経済活動を行う法人は、その経済活動から生じる利益について日本において課税されます。しかし、多国籍企業が日本において経済活動を行う場合、その進出形態によって税制が不公平にならないような措置がとられています。日本で設立された法人については、非課税や免税とされる一定の所得を除き原則としてその所得の発生場所(所得源泉地といいます)を問わず、その日本法人の所得が課税対象になります。その場合、外国において獲得された利益が含まれる場合で、その利益について所得の源泉地国で課税がなされているときには、所得源泉地国と日本での二重課税を排除する目的で、一定の範囲で外国において課された税を日本の税から控除する外国税額控除の規定が設けられています。一方、外国法人の日本支店については、一定の日本国内で発生した所得のみを日本で課税対象としているなど、日本において国際的に二重課税が発生しないような措置がとられています。
源泉徴収または申告納付
日本において活動を行う多国籍企業が、日本で課税対象となる一定の所得を得た場合には、その企業の形態およびその所得の種類により定められた方法に従い、源泉徴収による手続または申告による手続により税額が算定され、納付されます。
国内源泉所得
外国法人については、後述するようにその外国法人の日本における活動形態によって、法人税の課税範囲が異なります。また非居住者、外国法人の源泉所得税の課税対象となる所得を定めるために、国内源泉所得が以下のように定められています。
・一定の公社債の利子、国内事業所から生じる預貯金の利子
・国内業務にかかる貸付金の利子
・内国法人の株式、証券投資信託の配当
・国内不動産、その他類似財産の使用の対価、居住者又は内国法人に対する船舶または航空機の賃貸料
・給料、賃金、または賞与などの報酬で国内の役務提供に起因するもの
・居住者としての役務提供に起因する退職手当または年金
・国内での自由職業の役務の対価
・国内における芸能人、自由職業者または技術者などの人的役務提供事業の対価
・国内業務にかかる特許権、ノウハウ、著作権等の使用料または譲渡の対価
・国内業務にかかる機械装置の使用料
・国内の広告宣伝の賞金
・国内で締結された契約に基づき支払われる年金
・国内で発行される割引債の償還差益
・国内で生じる利子所得に類似する一定の所得
・国内不動産の譲渡による所得で一定のもの
・匿名組合契約に基づく利益の分配
・上記以外で国内資産の運用、保有、譲渡による所得で一定のもの
・国内事業所得
・民法に規定する組合契約等に基づく利益の分配
法人所得課税の概要(法人税・法人住民税・事業税)
法人所得課税と税率
平成24年4月以降法人税率は以下の通り移行することになります。
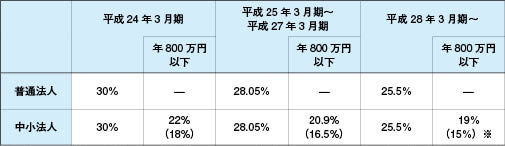
法人住民税 均等割課税分
| 資本等の金額 | 従業員数 | 均等割 |
|---|---|---|
| ¥5,000,000,000超 | 50人超 | ¥3,800,000 |
| ¥1,000,000,000超¥5,000,000,000以下 | 50人超 | ¥2,290,000 |
| ¥5,000,000,000超 | 50人以下 | ¥1,210,000 |
| ¥1,000,000,000超¥5,000,000,000以下 | 50人以下 | ¥950,000 |
| ¥100,000,000超¥1,000,000,000以下 | 50人超 | ¥530,000 |
| ¥100,000,000超¥1,000,000,000以下 | 50人以下 | ¥290,000 |
| ¥10,000,000超 ¥100,000,000以下 | 50人超 | ¥200,000 |
| ¥10,000,000超 ¥100,000,000以下 | 50人以下 | ¥180,000 |
| ¥10,000,000以下 | 50人超 | ¥140,000 |
| ¥10,000,000以下 | 50人以下 | ¥70,000 |
日本法人の設立、日本支店等の開設と税務届
日本の法律に基づいて新たに日本法人を設立した場合、または新たに日本に支店等を設置した場合には、その設立または設置後、一定の期限内に税務当局に対してその設置にかかる税務届出書類を提出しなければなりません。また、外国法人が支店等を設けないで国内において法人税の課税対象となる一定の所得を生じることとなった場合に該当することとなった場合)、または支店は設けないが以下に定める条件に合致する場所、もしくは人を通じて活動を行うこととなった場合にも税務届出書類の提出が必要です。
<支店を設けないで活動を行う外国法人が税務届出の必要があるケース>
国内において建設、据付け、組立て、その他の作業または作業の指揮監督の役務の提供を1年を超えて行う場合
以下にあげる一定の代理人を通じて事業を行う場合
その外国法人のためにその事業に関し契約を締結する権限を有し、かつ、 これを常習的に行使する者
その外国法人のために顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、その資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
専らまたは主として一つの外国法人のために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議、その他の行為のうちの重要な部分をする者
法人課税所得の範囲
日本で設立された法人は、その日本の国内、国外を問わず全世界で稼得された所得について日本において課税対象となります。一方、外国で設立された法人については、課税上、その法人を以下3つのいずれかに区分した上で、その区分に応じて、前述の国内源泉所得のうち、それぞれ定められた所得について日本において法人税、法人住民税、事業税が課税されます。ただし、3の区分の法人については法人住民税、事業税は課されません。
<外国法人の日本における活動様態と課税所得の関係>
日本国内に支店、出張所、事業所、事務所、工場等事業を行う一定の場所を有する外国法人
すべての国内源泉所得
※ただし、以下の場所はここでいう「一定の場所」に含まれないものとされています。
・外国法人が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他その事業の遂行にとって補助的な機能を有する事業上の活動を行うためにのみ使用する一定の場所
・外国法人がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所。
・外国法人がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所。
・事業所得および国内源泉所得のうち4、8、15、17に掲げた所得ならびにその他の国内源泉所得でその国内事業に帰せられるもの
駐在員事務所等の所得
いわゆる駐在員事務所等を通じて日本において活動を行う外国法人で、その事務所等が、広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究、その他その事業の遂行にとって補助的な機能を有する行為をする場合、その行為からは法人税の課税対象となる所得は生じないものとされています。
法人課税所得の算定
各事業年度の所得に対する法人税等の課税標準である所得の金額は、一般に公正妥当と認められた会計処理の基準によって算定された企業利益に所要の税務調整をして算定されます。以下に例示した一定の例外的な取り扱いを除き収益の獲得のために発生した原価、経費の額は控除できます。
外国法人の場合には、課税される日本国内源泉所得の算定上控除すべき原価、経費についてはその発生場所に制限はありません。ただし、国外で発生した原価、費用を国内所得の算定上控除するために配賦する場合にはその明細を作成しなければなりません。また、その配賦は定められた方法により適正になされなければなりません。
<原価、費用の控除に制限がある一定の項目の例>
・法人税等および罰科金
・寄付金の損金算入限度超過額
・交際費の損金算入限度超過額
・各種引当金の繰入額
・減価償却資産および繰延資産の償却限度超過額
・資産の評価減
・役員給与、役員退職給与
本国への送金
外国法人の支店が行う本店(本国)向けの送金については、原則として、その支払者である支店でその支払を経費として取扱うことはできません。
一方、日本法人が行う親会社(本国)向けの送金は企業間の取引に基づいて行われ、その内容にしたがい一般的に原価、経費の支払、利益の配当、または貸付け(もしくは貸付金の返済)等として取扱われます。その原価、経費のうち一定のものは支払者である日本法人の所得計算上控除されます。親会社の所得と取扱われる一定の支払(例えば利子、配当、使用料の支払等)については、その支払の際に源泉所得税の課税が必要になるものがあります。
同族会社の留保金課税
同族会社である日本法人のうち一定の法人については、通常の所得に対する法人税に加えて留保金課税の適用があります。留保金課税は、各事業年度の留保金額から留保控除額を控除して算出される課税留保金額に特別税率を乗じて算出されます。特別税率は所得の金額に応じて、年3,000万円以下の金額に対して10%、年3,000万円を超え年1億円以下の金額に対して15%、年1億円を超える金額に対して20%となっています。
欠損金の取り扱い
各事業年度の所得の計算上生じた欠損金額はその後7年間繰越されます。この欠損金の繰越制度は、欠損の生じた事業年度において青色申告書を提出し、かつ、それ以後連続して確定申告書を提出している場合に限り適用されます。また青色申告書を提出する中小法人等一定の法人については、欠損金の生じた事業年度の開始の日前1年以内に開始した事業年度にその欠損金を繰戻し、その繰戻しをした事業年度の法人税額の全部または一部の還付を受けることも認められています。
企業組織再編税制
法人が分割、合併、現物出資等(組織再編)により資産を移転する場合には、原則として移転資産の譲渡損益についての課税が行われます。しかし企業グループ内の組織再編あるいは共同事業のための組織再編等として一定の要件に該当する組織再編については、適格組織再編としてその移転資産の譲渡損益の課税を繰り延べる措置が取られています。
税務申告と納付
・確定申告と納付
法人は、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内にその所得についての法人税、法人住民税、事業税について税務申告書を提出しなければなりません。しかし、会計監査人の監査が終了していないことや、その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、確定申告書を提出することができない場合には、税務署長の承認を受けて、提出期限を延長するように求めることができます。この確定申告書に記載する所得金額や税額等は、株主総会の決議により確定した決算にもとづいて計算されなければなりません。
また計算された税額は同期間内に納付されなければなりません。上記により申告書の提出期限が延長されても納付期限は延長されませんので、延長期間中に納付した場合には、その期間につき利子税や延滞金(損金算入)が課されます。この納付すべき確定税額の計算上、予め納付された中間納付額がある場合にはそれを控除します。
・中間申告と納付
事業年度が6か月を超える法人については、その事業年度開始の日以後6か月を経過した日までの期間について、最初の6か月を経過した日から2か月以内に中間申告書を提出し、中間納付額を納付しなければなりません(定められた算式で計算された税額が一定額以下の場合を除く)。
・青色申告
法人の税務申告書は白色と青色の申告書に区別されます。法人は税務署の承認を受けて青色申告書を提出することができます。青色申告を提出する法人には各種の税務上の特典が付与されています。青色申告書を提出することについて税務署の承認を得るためには、一定の書式による承認申請書をその事業年度の開始の日の前日までに税務署に提出しなければなりません。新たに設立された法人や新たに日本において支店を設けることになった外国法人について、その設立(設置)した日の事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合には、その設立(設置)以後3か月を経過した日と設立(設置)後最初の事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに承認申請書を提出しなければなりません。
事業税の外形標準課税
資本金または出資金の額が1億円を超える法人については、所得、付加価値および資本金を課税標準とする外形標準課税が行われます。所得割、付加価値割および資本割のそれぞれの標準税率は以下のとおりです。
・所得割
⇒年400万円以下—1.5%
⇒年400万円超 800万円以下—2.2%
⇒年800万円超—2.9%>
・付加価値割—0.48%
・資本割—0.20%
・地方法人特別税—所得割に対して148%
※ 地方自治体により標準税率と異なる税率の場合がある。
源泉所得税の概要
所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」を建前としています。しかし、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。この源泉徴収される税を一般的に源泉所得税と言います。源泉所得税は個人・法人問わず課税対象となる一定の所得の支払が行われる場合に課税されます。源泉所得税が課税される所得は、所得の種類やその所得の受領者の区分に応じて定められています。
源泉徴収と納付手続
源泉徴収すべき所得の支払を行う者は、源泉徴収した税額をその支払を行った月の翌月の10日までに税務署に対して納付しなければなりません。ただし、支払者が日本に住所または事業所を有する場合で、その支払が国外において非居住者または外国法人に対して行われたときには、その源泉所得税は支払が行われた月の翌月末日までに納付します。居住者に支払う給与等の源泉所得税については、支給人員が10名未満の小規模事業者に限り、その所定の選択により、年に2回(7月10日までと1月20日まで)にそれぞれ6か月分の源泉所得税をまとめて納付できる特例が認められています。
居住者に対する源泉税
居住者に対して国内において行われる下記その他一定の支払は源泉徴収の対象になります。
・利子(特定の割引債の償還差益を含む)
・給与、賃金、賞与およびその他類似の報酬
・退職手当
・被用者以外の者に対する一定の報酬、料金等
内国法人に対する源泉税
内国法人に対して国内において行われる下記その他一定の支払は源泉徴収の対象になります。
・利子(特定の割引債の償還差益を含む)
・配当
・馬主が受ける競馬の賞金
・匿名組合契約に基づく利益の分配
非居住者、外国法人に対する源泉税
非居住者または外国法人に対して「国内源泉所得」の支払が国内で行われるとき、または、国外で支払われる場合でもその支払者が国内に住所等または事業所等を有しているときは源泉所得税が課税されます。このうち非居住者および外国法人の区分に応じて定められた一定の所得については、所得の受領者である非居住者または外国法人が国内に恒久的施設を有する場合には、その所得がその恒久的施設に帰属し、事業所得と合算して申告課税の対象になる旨の税務署の証明書を支払者に提示することを条件にして源泉徴収が免除されます。
租税条約
日本は所得税に対する国際的な二重課税の回避、脱税の防止を目的として多くの国と租税条約を締結しています。
租税条約の規定は国内法に優先して適用されます。締約相手国の居住者である者または法人に対する日本の課税については、租税条約にしたがって国内法で課税所得として定められている各種所得の所得源泉地が修正されることがあります。また各種所得に対して所得の源泉地である日本における税の減免規定が置かれています。
消費税の概要
次の国内取引および輸入取引については、非課税とされる一定の取引を除き消費税が課税されます。消費税の税率は5%(地方消費税1%を含む)の単一税率です。
・国内取引: 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供
・輸入取引: 保税地域から引き取られる貨物
・金融取引、資本取引、医療、福祉、教育の分野の一定の取引は非課税とされています。輸出取引や国際通信、国際運輸等
のいわゆる輸出類似取引は消費税が免税とされています。
申告・納付
国内取引を行う事業者(消費税の免税事業者を除く)や輸入取引を行う者は、それぞれ定められたた手続き、方法により課税標準に対する消費税を申告納付しなければなりません(事業者(免税事業者を除く)の課税標準に対する消費税額が、控除可能なものとして定められた方法により計算された仕入れに係る消費税額に満たない場合には、その満たない金額は申告をすることにより還付されます)。生産・流通の段階で二重に課税がされることがないように、仕入れに対する消費税を売上に対する消費税から控除する仕組みが取られています。
仕入税額控除
納付すべき消費税額の計算上、課税標準に対する消費税から仕入れ(他の者からの資産の譲り受け、借り受け、役務の提供をいいます。)に対する消費税を控除することができます。ただし、その控除額は課税売上割合によって制限されます。基準期間(*1)の課税売上高(*2)が5,000万円以下である課税期間については、税務署長に対して一定の届出をすることにより、課税標準に対する消費税にその業種について定められた一定の割合を乗じた金額を仕入れに対する消費税とみなして控除することが認められています。
免税事業者制度
基準期間(*1)の課税売上高(*2)が1,000万円以下の事業者(課税事業者の選択をしている場合を除く)は、原則としてその課税期間について納税義務が免除されます。ただし、所轄税務署長に納税義務の免除を受けないことについて届出書を提出することにより、課税事業者になることができます。また、新たに設立された法人等基準期間がない法人で事業年度開始時の資本金が1,000万円以上の場合は、その事業年度にはこの免税制度を適用することができません。
*1. 前々事業年度の期間が1年の法人は前々事業年度を基準期間とします。前々事業年度の期間が1年未満である法人については、その事業年度開始日の2年前の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間とする。
*2. 前々事業年度の期間が1年でない法人については、基準期間における課税売上高を1年分に換算した上で判定する。
法人のその事業年度について、現行制度において免税規定の適用を受ける事業者のうち、
次に掲げる課税売上高が1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度を
適用しないこととなります。
(a)法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始の日から6月間の課税売上高
(b)法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年内に
開始した前々事業年度があるときは、当該前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高
(当該前々事業年度が5月以下の場合、当該前々事業年度の課税売上高)
この規定の適用にあたり、法人は上記課税売上高の金額に代えて、給与等の支払額の
金額を用いることができることとなります。
※ 法人の場合は平成25年1月1日以後に開始する事業年度より適用
個人税制の概要
すべての個人は国籍に関わらず、居住者または非居住者に区分されます。個人に対する所得税は申告所得税と源泉所得税に分類されます。申告所得税は暦年中における個人の所得に対して課税されます。
居住概念と課税所得
居住者
日本国内に住所を有する者、日本国内に1年以上居所を有する者を居住者といいます。居住者に対しては、所得の源泉地を問わず全世界所得に対して所得税が課税されます。
※非永住者
居住者のうち日本に国籍を有しておらず、かつ、過去10年間のうち5年以下の期間国内に住所または居所を有する者は非永住者とされる。非永住者の課税範囲は居住者の課税範囲に準ずるが、国外源泉所得については、日本国内で支払われたり、日本へ送金されない限り日本では課税されない。
非居住者
居住者以外の者を非居住者といいます。非居住者については、日本の国内源泉所得についてのみ日本の所得税が課されます。前述のとおり、非居住者に対する源泉税の課税範囲を国内源泉所得に対して網羅的に規定しているため、特定の場合を除き非居住者については源泉徴収のみで課税が完結する場合が多くなっています。
※上記1において「住所」とは生活の本拠をいう。居所とは相当期間継続して居住する場所だが、生活の本拠という程度には至らないものをいう。
申告所得税
居住者に対する申告所得税
所得は各種所得に区分され、区分された所得ごとに定められた方法で所得金額が算定されます。その所得金額の合計額から各種所得控除を控除し、控除後の課税所得金額に下記の累進税率を乗じて税額を算定します。あらかじめ所得に課せられた源泉徴収税額がある場合には控除されます。
非居住者に対する申告所得税
非居住者はその態様により、(a)事務所などを国内に有する非居住者、(b)国内において建設、組立てを1年以上継続して行う非居住者または特定の代理人を通じて事業を行う非居住者、(c)その他の非居住者に区分されます。
その態様別区分により、それぞれ定められた範囲の所得について、課税所得が計算されます。非居住者に課される申告所得税額は、原則として居住者の場合と同様に計算されます(適用される所得控除等・外国税額控除の不適用など一定の制限があります)。日本で提供した役務に対して支払われる給与所得で海外において支払われたため、日本において源泉徴収されていない非居住者は、その給与等総額の20%の税額を申告して、納付しなければなりません(分離課税)。
個人の申告所得税(居住者の場合および非居住者の総合課税の場合)の税率は以下のとおりです。
個人所得税の税率
課税所得金額の区分 税率
¥1,950,000以下・・・・・・・・・・ 5%
¥1,950,000超~¥3,300,000以下・・・10%
¥3,300,000超~¥6,950,000以下・・・20%
¥6,950,000超~¥9,000,000以下・・・23%
¥9,000,000超~¥18,000,000以下・・ 33%
¥18,000,000超・・・・・・・・・・ 40%
源泉所得税
居住者および非居住者に対する源泉所得税のとおりです。
申告・納付
居住者は源泉徴収により納税手続が完了している場合を除いて、その年の所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出し税額を納付しなければなりません。ただし、合計所得金額が諸控除の合計額を超えない者や、支払先1か所から源泉徴収(年末調整)の対象となる給与の支払を受ける場合でその年の給与収入が2,000万円以下で、他の所得が20万円以下である者は、原則として申告の必要はありません。
非居住者の申告納付は、原則居住者の規定に準じます。なお、納税管理人を指定しこれを税務署長に報告することなく出国する非居住者は、出国前に確定申告書を提出し、税額を納付しなければなりません。
個人住民税・個人事業税
個人住民税は、個人所得に対する都道府県民税と区市町村民税の総称であり、各年1月1日現在日本に住所等を有する者について課されます。個人住民税は所得割と均等割(定額)等からなります。所得割は前年の所得について課税され、その課税所得の計算は特別のものを除き所得税の計算の規定に準じて計算されます。個人住民税の申告は、3月15日までにしなければなりませんが、所得税の確定申告書を提出する場合は改めて個人住民税の申告は不要とされています。個人住民税(所得割)の標準税率は以下のとおりです。
個人住民税(所得割)の標準税率
都道府県民税 一律 4%
区市町村民税 一律 6%
※均等割の標準税率は、道府県民税1,000円、区市町村民税3,000円である。
※地方自治体により標準税率と異なる税率の場合がある。
地方税法に定める一定の事業を行う個人は事業税を納付しなければなりません。事業税の課税所得は特別の定めがあるもののほか、原則として所得税の計算の規定に準じて計算されます。申告は3月15日までに行い、都道府県から交付される納税通知書にしたがって、8月と11月に納付しなければなりません。個人事業税の税率は事業の種類に応じて3%~5%です。
その他の主な税金
その他、所得、資産の取得や保有、消費等について各種の税金が課税される場合があります。資産の保有について課税される税で、多くの事業者に共通するものとして固定資産税(償却資産税)、都市計画税があります。固定資産税(償却資産税)は、土地・建物および事業用の減価償却資産について、各年の1月1日現在の所有者に対して1.4%の税率で課税されます。都市計画税は固定資産税の付加税として、都市計画区域内の土地・建物に対して0.3%の税率で課税されます。その他、東京や大阪などの大都市の事業者については、床面積が1,000平米を超える場合や従業者数が100人を超える場合には、事業所税が課税されます。税率は床面積1平米当たり600円、給与総額の0.25%です。
また、不動産や会社の登記、特定の営業免許等を受ける際に課される税として登録免許税があります。また規定されている文書を課税対象とした税として印紙税があります。上記のほか、贈与税や相続税、各種の目的税があるので留意する必要があります。
その他国際取引に係る主な法人税制
外国税額控除および外国子会社からの配当
所得に対する国際間の二重課税を排除するため、内国法人の一定の所得に対する外国税額を日本の税額から控除限度額の範囲内で控除することが認められています。この外国税額控除制度には、(1)内国法人が国外で得た所得に対して、自ら直接に納付した外国税額を対象とするもの(直接税額控除)、(2)租税条約の規定に基づき、条約相手国で特別に減免された税額を対象にする制度(みなし税額控除)、(3)いわゆるタックスヘイブン対策税制の適用により内国法人の所得に合算された特定の外国子会社等の所得に対応する外国税額を対象とするもの、などがあります。
また、2009年4月から、持ち株要件等を充足する内国法人の一定の外国子会社からの配当について、その一定額を課税対象から除外するという取扱いを通じて国際間の二重課税を排除する外国子会社配当益金不算入制度が導入されています。
移転価格税制
法人が国外にある親会社などの関連会社との取引価格を通常の価格(独立企業間価格)と異なる金額に設定し利益を国外に移転することを防止するため、その対価が独立企業間価格と異なることにより課税所得が少なくなる場合には、その取引が独立企業間価格で行われたものとみなして税額を算定することとしています。
タックスヘイブン対策税制
内国法人がいわゆるタックスヘイブンに所在する一定の外国子会社を通じて所得を留保することにより租税を回避することを防止するため、その外国子会社の留保所得のうちその持分に対応する金額を内国法人の課税所得に取り込み課税を行うこととしています。
※2010年4月1日以後開始する特定子会社の所得に対してこの規定を適用する場合については、適用対象となるタックスヘイブン(軽課税国)の判定税率(いわゆるトリガー税率)が「20%以下」に引き下げられたほか、適用対象となる子会社の株式保有割合が10%以上へ引き上げられるなど一定の見直しがされた。
過少資本税制
法人が一定の国外の支配株主から調達した借入金が、自己資本の3倍(あるいはこれに代わる合理的な比率)を超える場合には、その超過額に対応する負債利子は課税所得計算上控除できないこととされています。