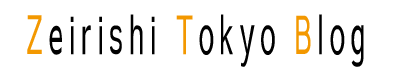中古資産の耐用年数は何年で計算すればいいのか?
中古資産を減価償却するためには、「法定耐用年数」ではなく「使用可能期間」を見積もる必要があります。
中古資産の耐用年数(使用可能基幹)の簡便法による具体的な計算方法について解説していきます。
合わせて、実際にどのように減価償却を進めていくのかをご紹介していきます。
中古資産の減価償却の概要については、『中古資産の具体的な減価償却方法について解説』にてご確認いただけます。
|-簡便法による見積耐用年数を使用した具体的な減価償却方法(定額法)
|-中古資産の購入価格が30万円未満なら少額減価償却資産の損金算入の特例を適用できる
|-まとめ
|-簡便法による使用可能期間の具体的な計算方法
それでは実際に、簡便法による中古資産の使用可能期間を具体的に計算していきましょう。
大枠となる基準は、以下のように定められています。
・法定耐用年数の全部を経過した資産:その法定耐用年数の20%に相当する年数
・法定耐用年数の一部を経過した資産:その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
始めに、法定耐用年数の全部を経過した中古資産の使用可能期間を求めていきましょう。
例えばここに、中古の太陽光発電設備があったとします。
法定耐用年数17年を経過していますが、メンテナンスすることでまだ十分に使用可能な状態です。
法定耐用年数17年を経過した中古の太陽光発電設備場合の使用可能年数は、
17年×20%=3.4年
となります。
使用可能年数には、以下の端数ルールが設けられています。
・これらの計算結果によって1年未満の端数が出た場合は切り捨てる
・これらの計算結果によって2年未満になった場合は2年とする
そのため、上記例の簡便法による見積耐用年数は「3年」と計算されます。
次に、法定耐用年数の一部を経過した場合を考えてみましょう。
10年経過した中古の太陽光発電設備があった場合は、以下のように計算すると「9年」という計算結果を求めることができます。
(1) (17年-10年)=7年
(2) 10年×20%=2年
(3) 7年+2年=9年
|-簡便法による見積耐用年数を使用した具体的な減価償却方法(例として定額法の場合)
それでは実際に、上記の算出した簡便法による見積耐用年数で減価償却してみましょう。
耐用年数17年すべてを経過した中古資産の見積耐用年数は「3年」でした。
太陽光発電設備の取得価額が60万円だった場合、
・1年目の減価償却費:20万円
・2年目の減価償却費:20万円
・3年目の減価償却費:19万9,999円
となります。
最終年度は残存価額が1円となるように逆算して減価償却を行います。
|-中古資産の購入価格が30万円未満なら少額減価償却資産の損金算入の特例を適用できる
中古資産の価格が30万円未満であれば、中小企業向けの特例を適用して損金算入することができ、減価償却をする必要はありません。
さらに、中古資産の購入価額が10万円未満であればその年の必要経費とすることのできる原則規定があるため、簡便法による見積耐用年数が2年以上でも全額損金算入することができるようになります。
まとめ
中古資産の減価償却方法はそれほど難しくありませんが、自己流で判断して間違えたまま減価償却を進めていくのは大変危険です。
できるだけ早めに専門家に判断してもらうようにし、具体的な指示を仰ぎながら会計処理する方法をおすすめします。
参考URL
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
【免責及びご注意】
読者の皆さまの個別要因及び認識や課税当局への主張の仕方により、税務リスクを負う可能性も十分考えられますので、実務上のご判断は、改めて専門家のアドバイスのもと、行うようにして下さい。
弊社は別途契約を交わした上で、アドバイスをする場合を除き、当サイトの情報に基づき不利益を被った場合、一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。